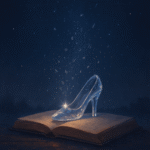GPTで、感情に寄り添うBotを作りはじめました。
1. はじめに
育児って、本音を話せる相手がなかなかいない。
ママ友やパパ友がいても、少し踏み込んだ相談は勇気がいるし、そもそもそんな時間さえ取れない日もあります。
そんな中でふと、「気をつかわずに、気軽に話を聞いてくれる存在がいたらいいのに」と思うようになりました。
そこから私は、“育児Bot”の開発を始めました。
私は普段、エンジニアとして働いています。ある日ChatGPTに「私にもできる副業ってある?」と相談してみたところ、「育児 × AI」というテーマが浮かび上がってきたのです。
ちょうど私自身も一児の母。
「エンジニアであり、母でもある自分だからこそできることがあるかもしれない」と思い、少しずつ挑戦を始めました。
2. 育児の悩みは尽きない。だからこそBotが必要だった
子どもが何歳になっても、悩みは尽きません。
日々のちょっとした不安やイライラ、戸惑いを、誰かに相談するのは案外ハードルが高いものです。
ネット検索をしても情報が多すぎて、かえって不安になってしまうことも。
「誰にも遠慮せず、本音で相談できたらいいのに」
そんな気持ちが、私にBotを作らせた一番の原動力でした。
3. Bot開発に使った技術と工夫
育児Botの開発には、以下の技術を使いました:
ChatGPT API(OpenAI) Streamlit:PythonでWebアプリを作れるフレームワーク Python(初心者でも扱いやすい言語) VSCode(エディタ) OpenAIのAPI設定・支払いまわり(ここが意外と難所!)
どれも初めて触れるものばかりで、最初は戸惑うことも多かったけれど、
ChatGPTに質問しながら、子どもが寝たあとの2時間×数日で、なんとか形にすることができました。
4. 初めてBotが返事をくれた瞬間
Botが初めて返事をしてくれたとき、思わず涙が出そうになりました。
「それ、つらいよね」「がんばってるね」
——そんな、たったひと言で、こんなにも救われるなんて思いませんでした。
そして気づいたんです。
アプリ開発って、思っていたよりずっと手が届くものなんだって。
エンジニア初心者でも、ChatGPTと一緒なら、自分の想いを形にできる可能性があるんだと。
「これ、続けていけばマネタイズもできるかもしれない」
そんな小さな自信も生まれました。
5. これから——育児もBotも、少しずつ育てていく
このBotはまだ試作段階ですが、今後はより使いやすく磨いていき、一般公開したいと考えています。
誰かが育児に悩んだとき、そっと寄り添ってくれるような存在になれたら嬉しいです。
私はエンジニアであり、一児の母でもあります。
そして今、育児をしながらでもBotを作ることはできるし、それを副業にもつなげられるという実感があります。
もし今、「私にも何かできるかな…?」と思っている方がいたら、
このブログが、あなたの一歩のきっかけになったら嬉しいです。
最後まで読んでくださってありがとうございます。言葉の魔法は、Xやnoteでもそっと灯しています。
▶ X(旧Twitter):https://x.com/sleepaftercode
▶ note:https://note.com/sleepaftercode